隣接権議論は“出版”をどう変えるか――福井弁護士に聞く(前編)(1/4 ページ)
時代に合った著作権とは何か。現在進められている著作権法の改正議論について、その全体像をつかむ本特集。前回の赤松健氏に続き、今回は知財に詳しい福井健策弁護士に話を聞いた。
著作権法の改正議論が白熱している。6月15日には、違法ダウンロードへの刑事罰導入を盛り込んだ著作権法改正案が衆議院本会議で可決されたが、改正議論はこれだけにとどまらない。
eBook USERでは電子書籍市場に大きな影響を与え得る出版社への著作隣接権の付与について、過去数度にわたって取り上げてきた。本稿はこの議論の本質を広く考えるために企画されたインタビュー特集で、第1回では、漫画家であり絶版コミックの無料配信サイト「Jコミ」を運営する赤松健氏に著作権者の立場から話を聞いた「赤松健は隣接権とそれを巡る議論をこう見る」をお届けした。
これに続く第2回では、過去にeBook USERでもスキャン代行訴訟などについて知見を示していただいた福井健策弁護士に、主に法制度の観点から見解を聞く。
福井健策(ふくい・けんさく)
弁護士(日本・ニューヨーク州)骨董通り法律事務所代表パートナー 日本大学芸術学部客員教授
1965年生まれ。神奈川県出身。東京大学、コロンビア大学ロースクール卒。著作権法や芸術・文化に関わる法律・法制度に明るく、二次創作や、TPPが著作権そしてコンテンツビジネスに与える影響についても積極的に論じている。著書に『著作権の世紀 ――変わる「情報の独占制度」』(集英社新書)などがある。「自炊」についても多くのメディアでコメントし、ニコニコ生放送『ネットの羅針盤』『「自炊」と電子書籍』にも出演。Twitterでも「@fukuikensaku」で発信中
ネット化への対応を迫られる著作権
―― 前回お話を伺った際、福井先生も指摘されていた「集中管理機構」が、日本漫画家協会からの「出版者(社)への『著作隣接権』権利付与に対する見解」というリリースにも触れられていましたね。
福井 踏み込んでますよね。こういった議論をするときに、必ず当事者が「流通促進」という観点を踏まえて語るようになったのは大きな変化だと思います。作品を必要とする人々に対して幅広く届けながら、どう収益を上げていくのか、ということに社会の視点が集まってきたかなと。
―― 議論のベースができてきた、ということですね。文化の保護や振興を前面に押し出すようなものではなく。
福井 文化の振興はもちろん著作権制度の第一原理です。でも従来は、作品やそれを生み出す人々への敬意=リスペクトを著作権と結びつける議論がすぐに前面に出てきた。リスペクトは大切ですが、それは著作権の役割ではありません。
というより、どんな法制度にも心の中の尊敬を担保するような力はない。
―― 制度でリスペクトまでは生まれない?
福井 制度でそれを強制することで、「尊敬」や「愛」というものの最も根本的な部分が奪われてしまうのではないか、という危惧すらあります。
出版社には何の権利もない
―― 流通を促進し、収益が十分確保でき、その結果次なる創作に繋がっていく、というプロセスがいま求められているわけですが、それを考える前にまず現状の出版社の権利がどうなっているのか、から解説いただけますか。
福井 簡単に言われましたが(笑)。分かりました。
原則論を言ってしまうと、出版社には放っておくと何の権利もありません。業界慣行としての「権利的なもの」はありますが、法律上当然に与えられるようなものはない。出版社自身が著作者に当たるような例外的な場合を除いて、出版社の権利は著作者(作家)との合意から生まれるのです。
そして、作家との合意内容によって大体4つのパターンで出版社に権利が生じてくると考えられます。
- 作家から著作権の譲渡や部分譲渡を受けるケース
- 出版権が設定されるケース
- 独占・排他的に出版の許諾を受けるケース
- 非独占的に出版の許諾を受けるケース
1.は専門書や百科事典などでよく見られるケースです。3.と4.は、著作権を持っている作家から出版を許可して貰うケース。著作権自体はあくまで作家の下に留まります。
―― 4.のようなケースもあるのですか?
福井 例えばアンディ・ウォーホールの作品を管理する財団から、作品写真の雑誌特集への掲載許可を受ける場合を想像してください。そのような場合は独占的な掲載はまれで、ほぼ間違いなく非独占的な許諾になるでしょう。
2.の出版権の設定についてお話ししましょう。これは1.の著作権の部分譲渡とやや近いのですが、3年〜5年と言った期間を設定するのが一般的です。その間、著作権の中の一部である「出版という形で作品を複製する権利」を、作家から出版社にいわば「移転」するのが出版権です。これを「出版権の設定」と言います。
以上はすべて「作家=著作権者との合意」がなければ生まれません。出版権の設定も同様です。出版権の特徴は、期限があることに加え「紙にしか及ばない」と一般に考えられている点。少なくとも現在主流の電子出版のスタイル、つまり「配信」には及ばない。
出版契約書には、2.のような出版権の設定、もしくは3.のような独占的な出版の許諾が記載されていることが一般的です。私の経験だと書籍では出版権設定が書かれていることが多い。雑誌はそもそも契約書が交されることが少ないですが、書面はなくても口頭なりの合意として、出版許諾などがされていると見なされるはずです。
さて、こういう状況の中、いわゆるKindleショックやGoogleショックといった出来事が起こりました。電子出版の波が襲ってきたわけです。日本の出版界も改めて電子出版対応を迫られ、また同時期にネット上に海賊版が数多く出回る現状にも注目が集まるようになりました。こちらにも対応をしなければならない。
そこで出版社がハタと迷ったのが、「電子出版の権利を自分たちが持っているのだろうか」ということでした。もちろん契約書でそれを確保しているケースもありましたが、出版契約書の普及率はこれまで非常に低かったのです。2006年3月の調査で新刊書の45.9%しか契約書が締結されていませんでした。その後急速にこの比率は上がってきてはいますが、それは新刊書だけですから、既存の書籍には契約書がないケースが多いわけです。
つまり契約書には頼れないケースが多い、そうなると、作家と出版社の間には何があるのか。口頭か暗黙での出版権設定(上の2.)もしくは排他的な出版の許諾(上の3.)がある――恐らくそうなんだろう。でも、それでは電子出版に権利は及ばなそうです。仮に契約書を交わしていても、そこに出版権の設定としか書いていなければ、同じことです。現行法での「出版権」は電子配信には及ばないのですから。
では出版社は完全に埒外なのか、というのは早計で、業界慣行や各種の力学というものがありますから、いまのところ作家が出版社に相談なく既存作品の電子化を進めるといったケースは少ないでしょう。しかし、電子書籍で「出版社の権利」と言えるほどのものはない場合が多いのも、また事実なのです。
そうなると、少なくとも理論上はこういったことが起こり得ます。ある作家さんが、出版社から紙で本を出した翌週にAmazonなどで自ら電子書籍を出してしまう――これが可能になると、出版社としては困るでしょう。
また、海賊版の取り締まりについても、出版権は電子書籍には及んでいませんから、出版社は自ら訴訟は起こせない。作家に「弁護士は紹介しますから、原告として訴訟を起こしてください」とお願いしなければならない。多くの作家はこれを嫌がります。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

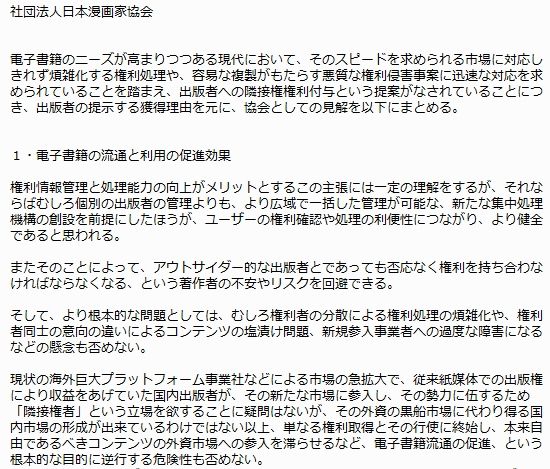 日本漫画家協会から出された「出版者(社)への『著作隣接権』権利付与に対する見解」より一部引用
日本漫画家協会から出された「出版者(社)への『著作隣接権』権利付与に対する見解」より一部引用 福井健策弁護士
福井健策弁護士